top of page

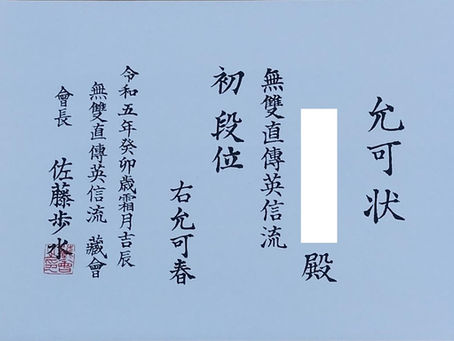
無雙直傳英信流 武蔵野稽古会の系譜 其之四
福井宗家の次代、二十二代池田聖昂師への継承後、福井聖山師と当代における教義の差異により、また一門に亀裂が生じます。 福井宗家直門、宗家継承候補者で関東地区連盟会長でもあった江坂静厳師も、二十二代池田聖昂師の傳承術儀と相容れず、別団体を発足し全日居を脱退されました。...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


無雙直傳英信流 武蔵野稽古会の系譜 其之三
二十一代宗家は先述の条件により、河野百錬師の次は高知人へ承継されるはずでしたが、河野百錬師が次代継承者を指名せず急逝されたことにより、全国へその門下を拡げた一門の内部では承継者問題が起こりました。 結果として、全日居の中核である無雙直傳英信流(正統会)は岐阜の福井聖山師が二...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


無雙直傳英信流 武蔵野稽古会の系譜 其之二
幕末当時、土佐の伝承は大きく分けて谷村派と下村派の二つが主流でした。 大江正路師は若年期に下村派を学び、戊辰戦争へも出征、明治に入り谷村派十六代後藤正亮師に師事し谷村派を修業、谷村派十七代相傳者、宗家となりました。 一方下村派においても十四代下村茂市師、十五代行宗貞義師、同...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


無雙直傳英信流 武蔵野稽古会の系譜 其之一
無雙直傳英信流は神夢想林崎流、田宮流などの古流居合流派と同じく、室町時代の武芸者 林崎甚助源重信が山形県楯岡林崎にて開眼、創始した居合術の直系を標榜しています。 当会 無雙直傳英信流 武蔵野稽古会の道統としている系譜では、七代相傳者に長谷川主税助英信師という達人があり、この...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


稽古と云う事
よく言われるように、稽古とは本来「古(いにしえ)を稽(かんがえる)」という意味を持ちます。 当流の様に、江戸時代以前の古流を源流とする武道ではよく「練習」ではなく「稽古」といいますが、これはまさにただの反復練習ではなく、いにしえをかんがえる事もその眼目にあります。...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 4分


真剣を遣う事について
居合とは居合わせの武術であり、刀剣による技術に限られず、己の身、身の回りの物、地の利、時の利すべてを利用して敵を制するすべが本来の姿です。 古傳では172本(神傳流秘書を中心に、同書にある併傳柔術夏原流を含めた166本、時代ごと複数ある伝書の重複は同書に集約し、英信流目録二...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 終わりに
まとめ 以上が当会に伝わる、基本中の基本となる礼法、伝承です。 序文にあるとおり、あくまで当会に伝わる伝承を、当会の居合道としての修行に供する目的として細部まで分解、且つその所作が持つ意味を考えてみました。 不肖の文章力不足もありますが、武術、武道における文字による解説とは...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 1分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之十二
そのほかの伝承 二 ・重心の事 重心においては「嚢に重しを下げたる心持」(これは英信流の口伝であったか、不肖の別武術での口伝であったか、曖昧です)とし、これも古流武術にみられる重心の意識を下に置く心持と同義と考えます。 立ちながらの業においては重心が上がらぬよう、浮身の際は...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之十一
そのほかの伝承 一 鷲の爪の事 直立の時に、空いている手の親指を軽く握り込む事を清田泰山師より「鷲の爪」と教わりました。 同流、同系統の道場であっても、直立の姿勢は指先を揃え伸ばす道場も多く、果たして道統の教えなのかは不明です。...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之十
礼法 六 刀礼、帯刀 三礼の最後、刀礼を行います。 神前の拝礼後着座し、左手の刀を座礼に同じく右手に持ち替えます。 右手で持った刀の鐺を、膝から前方一尺程、右膝の右斜め前に着き、鐺を軸として柄頭を左へ寝かせ、静かに我が正面へ横たえます。...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之九
礼法 五 神前の拝礼 次に神前の拝礼を行います。 当会や、会長や不肖の在籍した道場では、武神として当流始祖とされる林崎居合明神の神棚を道場正面に戴き、拝礼します。 本来は道場の北、または西側の壁に神棚を戴くべきですが、稽古している武道場のレイアウト上致し方ない場合は道場入口...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之八
礼法 四 師範に対する座礼 師範に正対し着座したら姿勢を正し、心を落ち着けます。 左手に持った刀を体の正面、刃を我に向け膝から一尺の処へ鐺を着け垂直に立てます。 左手で握っている辺りに右手を添え、下緒ごと右手に持ち替えます。...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之七
礼法 三 正坐の座し方 支度が整ったら、師範及び道場に対する座礼、神前の拝礼、刀礼の三礼を行います。 まず師範、道場への座礼を行います。 これは本来、師範に対する礼でもありますが、当会では仕事や家庭の都合で稽古開始時間に来られない人もいる為、稽古開始時間に間に合わなかった時...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之六
礼法 二 立姿勢 彼我の挨拶は道場としてのルールというより、一般常識です。 そのうえで入場時、作法としてはまず道場に入る時に一礼して、場内に入ります。 この際、右足から踏み込みます。 あいにく師よりこの理由は伝えられていませんが、殿中の礼法であった伊勢流に拠る利き足から立て...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之五
礼法 一 刀の持ち様 刀は本身であれ模擬刀であれ、道場以外の場所では移動中を含め「すぐに抜くことが出来ない」状態であることが大原則です。 基本的には刀袋で包み、刀ケースに収めて持ち運びします。 刀ケースは、知っている人から見れば中身は一目瞭然ですが、しっかりしまってあると判...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之四
着装 四 下緒 着装の最後に、刀の下緒について記しておきます。 本来打刀の下緒は、戦場に於いて腰帯に絡めたり、左右から胴に回し右腰で結ぶなど、鞘ごと抜け落ちないように付けられたのが始まりと云われています。 戦の無くなった江戸中期頃より、襷に使う、塀や崖を越える時に刀を足掛か...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之三
着装 三 足袋、礼装 足元は常の稽古では裸足、または紺、黒の足袋を履きます。 当会会長と不肖の歩んできた全日本居合道連盟、神州居合道連盟がそうであったことに準じ、白足袋は師範、または八段位以上のみ着装可、但し神前での演武では段位に関わらず礼装である白足袋が好ましいとしていま...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之二
着装 二 袴 袴の丈は、直立の状態で踝が裾に隠れる程度とされています。 あまり短いと足捌きの稽古にならず、長すぎると刀を持ったまま躓くなどして危険です。 柔術や合気系の流派では、師範、高段位の先生のみ袴を着用とする処もありますが、これは運足の秘事を隠すため、と聞いたことがあ...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 其之一
着装 一 角帯 稽古着は前合せの着物、角帯、袴を基本とします。 常の稽古では、着物は和装であれば基本自由、袴は股下の別れた馬乗袴型とします。 また指輪、腕時計、イヤリング等の装飾品は外します。 これは道場に対する礼儀であり、怪我の防止、また稽古中に刀を傷めたりしない為でもあ...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 2分


武蔵野稽古会傳 作法 細論 序文
序文 現在、諸事情により新規入門の受入れを中止しており、門下生にも稽古に通い難い条件となっております。 このような状況ですが、稽古は刀を振るだけではなく今一度、道としての意義を考えることも稽古であることを認識して貰いたく、本稿を連載します。...
武蔵野稽古会 無雙直傳英信流
7月16日読了時間: 3分
bottom of page

